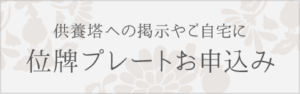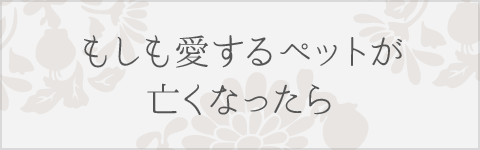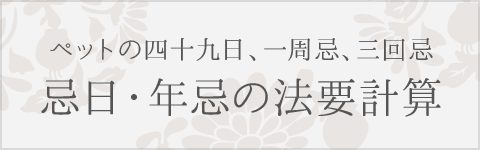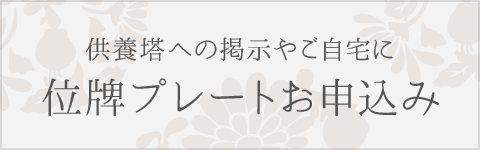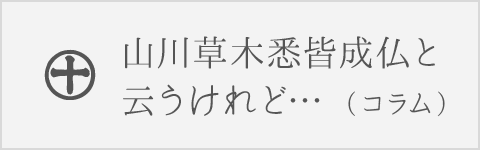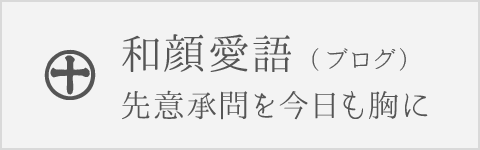日本人のペット供養と位牌文化について…②~妙円寺も位牌から建立された~
日本人とお位牌の深い絆
お位牌――
それは、故人の魂がやすらかに宿る、祈りのかたち。
日本人は、はるか昔より、この小さな御札に深い信仰と感謝の想いを込めてきました。
鎌倉時代、禅宗寺院では、ご本尊の両脇に位牌を安置する習わしが生まれ、
その人の魂が安らぐ場所、「菩提寺」という概念が広まります。
菩提寺に一つ、ご自宅に一つ、さらには分家にも――
日本人は、時を超えて魂を敬い、拝み続けてきたのです。
明治時代以前、実は「遺骨」よりも「位牌」が重んじられていました。
位牌はただの記しではなく、
「その人そのもの」として祀られる存在だったのです。
時を遡れば――
640年前、戦国大名・大内義弘の姫君のために造られた位牌には、
「法智 妙圓 霊位」という戒名が刻まれました。
この位牌が、やがて「法智山 妙圓寺」という寺院そのものを生み出し、
今日までその名を残しています。
一つの戒名が、歴史を刻み、寺を築き、祈りの場を守ってきたのです。
今、私たちはその祈りの伝統を、現代に受け継ぎます。
ご自宅用位牌プレートとして、また新たな「授与品」として――
小さな祈りのかたちが、また一つ、新たな絆を紡いでいきます。
日本人とお位牌の歴史
鎌倉時代から禅宗寺院では、ご本尊の両脇に位牌を安置する慣習があります。
その人のお位牌がある寺院を「菩提寺(ぼだいじ)」と呼びます。
菩提寺に一つ、自宅に一つ、分家などにも一つ祀り
日本人はお位牌を古くから、とても大切に拝んできました。
明治時代になるまではむしろ遺骨よりも「位牌信仰」が強かったほどなのです。
‐位牌はその人その子そのもの‐という概念が深く根付いていました。
(この春から授与品としている、とそ動物霊園の自宅用位牌プレート)
一つの位牌が妙円寺を建立
法智山妙圓寺の山号と寺号の由来となった、
長州の戦国大名大内義弘(毛利家の前と言えば解かりやすいかも知れない)のお姫様の雲首位牌。
640年前・戒名は “法智 妙圓 霊位”(最上段右から2番目)
一つの戒名が位牌と法智山 妙円寺をも建立した。
室町時代に長州の戦国大名が薩摩の伊集院に妙圓寺を?なかなか信じてもらえずに苦労したこともありましたが、
長州に現存する石屋真梁派の寺院をみれば、なぞの歴史は必然と紐解かれます。
例えば現在、妙圓寺=で有名な島津義弘はこの200年後に登場するという事になるわけです。
(お墓参りが絶えない合同供養塔と掲示用位牌プレート)
❐亡きあの子を供養塔の位牌プレートに祀り月例供養祭で読経シャワーなど浴びれば、
三界萬霊に憂い無し
記事:伊藤憲秀@kensyu_ito