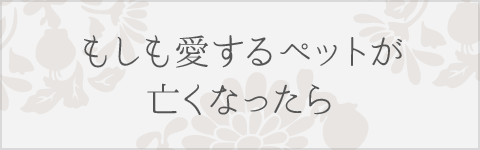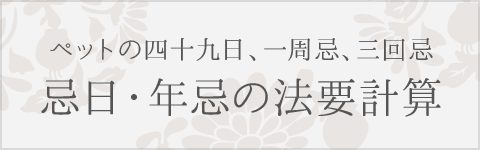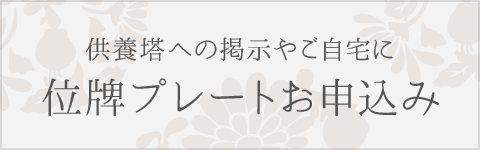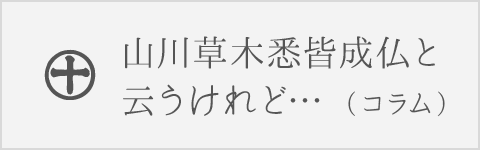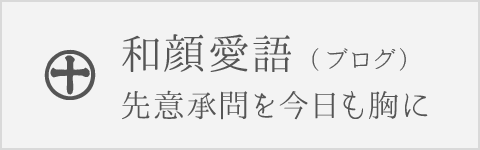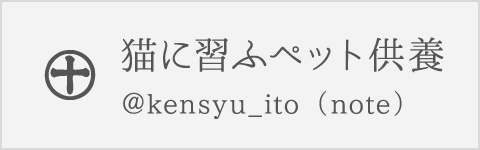虹の橋と三途の川といくつかのことについて…〜「ペットの死」と「火葬」からの旅の始まり〜
お別れが多く重なった日にはこんなことを考えてみたりする事もある…
仏教寺院の中には、
曹洞宗(禅宗)のように「確かにあるのであろうが、決してそれに囚われ過ぎてはいけない」的なスタンスで、
それと同じ考え方の宗派もあれば
そもそも「初めから、そんなものは無い」となる宗派もある。
むしろそれに対してウェルカムで積極的な宗派もあるでしょう。
それはつまり「幽霊」「霊的現象」「心霊現象」などについてである。
例えば曹洞宗の私の知っている寺院について。
曹洞宗に関しては「座禅」を軸とした実践的宗派であって「幽霊などはあなたが弱いからそのようなものが見えるのだ」とたしなめるのであろうと理解するが、
長い歴史の中で寺院の存在、由来自体が幽霊絡みの寺院すらも多く存在するのも事実だ。
○例えば、熊本県にある曹洞宗寺院永国寺は池に現れたという幽霊の掛け軸が現存する人気の観光スポットだ。
○死者とイタコが集うという、霊場青森県の恐山にもなぜか円通寺という曹洞宗寺院が存在する。
○また、鹿児島県日置市伊集院町の曹洞宗寺院、妙円寺も西国覇者の戦国大名、長州の大内義弘公の息女の霊を鎮めるために建立されたのが始まりである(薩摩の島津義弘は約200年後に妙円寺に帰依)
さて、一見、ペット葬儀となんの関係があるのかという文面になってしまったが、十年以上ペット葬儀に携わってきた者として、火葬の「まえとあと」の現象を紡いでみたいと思う。
いわゆる「愛する我が子の死と、虫の知らせ」のような事象と、その後について…。
○あの子が旅立った晩、二匹の蝶が窓にとまって長い間動かなかった、だとか。
○ある人はあの子が火葬された夕方、もしくは故郷の愛犬の訃報を電話で聞いた日に、
雲の姿に変えて現れただとか。よく耳にする話である。
いわゆる「虫の知らせ」である。
三途の川と、虹の橋と、いくつかのこと。。
ペットが死んだらどうなるのか。
「虹の橋のたもと」
ここ二十年で、ネットの普及による影響も強いと思われますが、急速に信じらていったというか、有名になった架空の話です。
ペットちゃんは、亡くなったら虹の花のたもとで飼い主を待ちわびていて、心の奥に引っかかりをもちながら暮らしているという話でした。
しかし、虹の橋のたもとで主人を待ちわびて暮らしているというペットが「可愛そうではないかと」「結局、ペットは死んでも寂しい思いをするのだな」との人々の意見により、今では、ペットちゃんが亡くなったと同時に「虹の橋を渡った」などの表現なってきています。
もちろん、この「虹の橋」の話に宗教的要素は一切ありません。
しかし、いつの日か虹の橋のお話にも「月のうさぎ」や「三途の川」のように仏教と融合する日が来るのだろうか…。

❏そして最後は、その三途の川、初七日の日に死者が船で渡るとされている川である。
この話はもともと民間信仰だったものに仏教がひっついた形のものである。
平安時代までは「虹の橋を渡る」と信じられていましたが徐々に変化し、六文銭を船頭に払い船で渡るとされています。
本当にもし、そうなんだとすれば…
あの子はあなたに愛された思い出を宝物に、胸を張って向こう岸まで無事に渡ることだろう。
冥土の旅の無事を祈るという言葉があるように、その後いろんな世界を旅をしてゆくと云う。
そしていつの日か、あなたがこの世での役目を終え、三途の川を渡るとき、向こう岸にちょこんと座って、嬉しそうにあの子が待ってくれているのだとしたっら。。
「死」というものには誰も逆らうことはできません。
「死」に対しては誰もが無力です。
「死」逝ってしまったあの子と同じように、我々もそれに向かって今を生きています。
だからこのような、一連の途方も無いような説話にすがるのかもしれません。
しかし、それでいいはずです。何を信じようが信じまいがあなたの心の落ち着きが大切です。
私達は今日も生きていくということだそう。辛くてもそうするしかないのです。
あの子との別れを、いない寂しさを思えば、胸が張り裂けそうなときもあるでしょう。
でも、あなたの悲しむ姿を一番心配しているのは亡くなったあの子です。
その日その日を大切に生きて行きたいですね。あの子にまた会える、その時がくるのなら…。
-「死」は生命最高の発明である。スティーブ・ジョブズ-
※当サイトの文章・絵などの無断転載・複製はいかなる場合も禁止いたします。
鹿児島のペット葬祭・火葬・葬儀・供養
妙円寺 慈愛の丘 とそ動物霊園